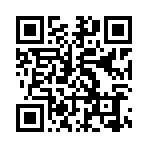2022年05月24日
中国・香港の長期ビザを永住権に切り替えずに7年更新することは可能ですか?

最近、多くの良い友人は、ビザ処理の更新フル7年は永住権をオンにしないについて私に言った、どちらか国内の実際のID、または海外の人々をキャンセルす香港工作簽證るアプリケーションの後に永住権を申請したくない、フル7年は永住権を申請するために香港に戻るには便利ではありません。 では、ビザ取得後7年経過しても永住権を申請しない場合はどうすればいいのでしょうか? ビザの更新は可能ですか?
移民局では、7年後に永住権を申請しなければならないとは定めていませんが、7年後に再度ビザを更新することは可能です。
就労ビザ
更新方法は、7年後に申請者のビザの処理の更新は、ビザ処理の最後の3年の有効期限が切れた後、永住権を申請したくない場合は、2 + 3 + 3は、パトロンが再びできるビザで仕事を更新するために事前に関連情報を準備させて、香港の期間はパトロンを変更する場合にも、ピンクのビザを変更する必要があることを忘れないでください。
ビザは優秀な人材のためにある。
更新方法は2+3+3、多くの人は就労ビザよりメリットビザの更新がとても簡単だと言いますが、ここで皆さんに注意しなければならないのは、メリットビザの更新も「決済内容の通常の住所として中国香港を使うかどうか」の規制を受けること、期間中の中国香港との関係があまり大きくなければ、更新申請の担当者は、おそらく 中国・香港と大きな関係がない場合、更新申請の担当者は、その年の実績に応じて、1年間のみビザを許可すると思われます。
IANGビザの手続き。
更新方法は1+2+2+3、初年度はIANGの理由はなく、その後の更新は中国香港のパトロンが必要です。
採用されたビザの手続き。
更新方法は、一般的に主な申請者に従いますが、主な申請者のいくつかの良い友人が永住権をオンにする必要があり、フォスターの対象は、ビザの処理を養うために永住権の主な申請者で、永住権をオンにしない常に更新する必要があります、一度壊れたフォスタービザの処理に適用するローンのスポンサーのための主な申請者を使用することができなくなります。
関連記事:
想迅速得到香港工作簽證?先看一下有什么可以留到香港工作的簽證辦理
中国・香港の駐在員が出国ビザを申請し、早期に入国するための提案(中国に来る外国人)。
2022年05月18日
千年の夢-水上ワインの過去と現在|One Moment to Share

日本酒の過去世
日本酒と同世代!
中国の農耕時代に端を発し、日本列島に深く根付いた農耕文化と酒造りの技術は、その後も進化を続け、現在のようなユニークで貴重な酒を生み出しました。
日本酒の "古参 "として、"初心者 "に日本酒日本清酒をどう紹介すればいいのか、具体的に考えてみました。 香りや味わいの多様性でしょうか。 あるいは、周囲の温度によって変化するニュアンスのある味わい? あるいは紛らわしい「専門用語」?
ワインの色、香り、味、風味について、合理的で尊大な説明は、素人を「いい気分」にさせるかもしれないが、それは、さまざまなワインが林立する中で、人を迷わせる誤解なのである。 では、どのような工夫をすればいいのでしょうか。 その答えは、モノそのものを超え、歴史や時間、文化や芸術に目を向け、そして現在を振り返り、すべてがどんどん正しくなっていくことです。
日本酒=日本の水上酒
日本人は日本酒を四川の瀘州老酒と見て、すぐに「日本酒」と呼び、この独特の愛を世界に発信しているようなものだ。 しかし、東京の街を歩き、多くの日本料理店に入ると、飲んでいる人が多くなり、焼酎やウィスキーのハイボールまであるように見えた。
この水割りの酒を愛する気持ちは、日本人にとって誠実なものなのかどうか、気になりませんか?
また、米と水から作られるのは日本酒ではないのでしょうか。 日本人が日本酒を「日本水」に変える勇気を持ったのはなぜか。 そして、日本酒が日本を脱出し、ヨーロッパ人に受け入れられるようになったのはなぜか。 今の日本酒でも、中国由来の遺伝子を見つけることは可能なのでしょうか?
この疑問を解明するためには、400年前に江戸城に伝来した日本料理の中に入っていかなければならない。
1 日本料理と日本酒
1603年、徳川家康は日本の戦国時代を終わらせ、江戸を中心とした新しい時代を切り開いた。 江戸時代中期には、あらゆる階層の人々が集まり、数百万人規模の大都市が誕生した。
また、新しい大都市を建設しなければならず、大量に採用された労働者はすべて男性であった。 一日中働きづめの独身者たちは、一日の終わりの一杯が何よりの楽しみだった。 仕出し弁当の営業を任された煮売り茶屋は、この大きな市場のニーズに応え、次第に酒を売るようになった。 そして、日本料理が確立された。
もふ」によると、江戸城内には2,000軒以上の日本料理店があり、現在の東京の546人に対し、約553人が日本料理店を持っていたという。
江戸舞台酒家
日本料理の決め手は、もちろん日本酒です。 もし、江戸時代にタイムスリップしたら、夕暮れ時の道を歩いている大酒飲みに出会うかもしれませんよ。 大坂に住んでいたペンヒコというマニアックな歌手の書いたジョーク集「軽口ペンヒコ杜」(寛政7年)は、三都を「江戸、京都、大坂」とし、「江戸は酒ばかり」「京都は服ばかり」「大阪は食ばかり」と表現している。 大坂の人間から見れば、江戸はもっと酒好きの大都会であった。
19世紀初頭、江戸の人々は年間90万樽以上の酒を飲んでいたという。 問題の「バケツ4杯」の容積はバケツ3杯分と5リットル程度なので、90万バケツは実質56,700リットルということになる。 当時の江戸の人口を100万人と仮定すると、1人当たり1日155mLの酒を飲んでいたことになる。
江戸の人々は、これほど大きな市場ができたことを大変喜び、関西の総量が目に見えてわかるようになっただけでなく、大阪と神戸の中間の地域に日本で最初の酒造業が誕生したのである。
関連記事:
さあ! このチューハイを作って、日本の水炊きに関する短い物語を語らせる。